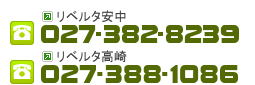●難民支援を今になって国連総会であえて表明する真意・思惑は?
9月30日「9月29日午後(日本時間30日午前)、安倍首相は米ニューヨークで開かれている国連総会で、シリアなどの難民支援に今年1年間で昨年の約3倍となる約1.8億ドル(約970億)を拠出することを表明。また安全保障関連法が成立したことを報告し、国連平和維持活動(PKO)に一層貢献していくことを訴えた」とのマスコミ報道がされました。単刀直入にこの報道を見聞きした皆様方は、率直にどのようにお感じになりましたでしょうか?
まさに言葉の通り「世界が直面するシリア危機、シリア難民支援に対し、日本がいよいよ本腰を入れ始めた朗報」「安保関連法成立を御旗に世界に貢献していく覚悟を示し始めた」と肯定的に受け止められた方も当然多くいらっしゃったことでしょう。確かにこの言葉や表現そのものは、当たり前に正しく間違ったことは一つも言っていない正論だと私も思います。
しかしながら、ここからはわたくし個人の考えですが、本当に心奥の底からあふれ出てきた言葉なのか?思いなのか?には疑念を持たざるを得ませんでした。と言うのも、例えばこれまでの過去の安倍首相の言動を振り返ると「国民の声に耳を傾け丁寧に説明してゆく」と言っておきながら実際の行動・態度は「自らのエゴを真っ先に優先し、国民の声をないがしろにする」と言った「言行不一致かつ不誠実な態度・言動」をこれまで幾度となく見せつけられてきたからです。事実「国民は一時的には反対の声を上げても、一旦ことを決めてしまえば後は時間が経てばいずれどうせ忘れてくれる」と言った感覚で完全に国民を見下しているところがうかがえます。そして今回の国連総会での表明やその後の記者会見の安倍首相の発言光景を見ていると、そのメッセージの先にある重要な相手は、世界有力国の首脳陣であり、国連関係者と取り巻くマスコミであり、それを経ての世界の人々に、日本と自分の威信を誇示することに最優先の情熱を傾けている様子がありあり感じられます。事実あれだけ美辞麗句を並べ立て、正義の味方を前面にだし、これから日本は世界の為に素晴らしい偉業を行うのだとでも言いたげな得意げな様子には、日本国民に向き合うときとのあまりにも真逆の態度の違いに、違和感を持たざるを得ませんでした。
事実、この後国連総会演説の後の記者会見も含め、印象としては色濃く残ったのは、安保法制を引っ提げて経済的にも軍事的にも世界の中枢、列強国、つまり国連安保理の常任理事国入りしたいというのが、最大の本音であることがあらためて明らかになりました。と同時に、本年4月29日安倍首相が米国連邦議会の上下両院合同会議においての演説での様子をだぶらせて思い浮かべました。この時も本来なら、まずは日本国内の国民に対してこそ、真摯に丁寧に説明をはじめ、国会等での様々な議論を得て、その方向性を決めていくはずのこの段階では未確定段階の安保法案を、米国上下両院議員に対し「この夏までに成就させます」とはっきり明言し、しかも聴衆のスタンディングオベーションに、まるで子供が親に手土産を携え喜ばれたことに機嫌を良くして喜ぶ欣喜雀躍ぶりには、違和感・不信感・不快感を通り越し、開いた口がふさがらなかったのは決して私だけではないことと思います。あの時の喜びようは、まさにアメリカという親分、兄貴にほめられたい使いっ走りの子分・弟分のごとくであり、しかも彼が一番大事にしているのは紛れもなく決して国民でなく、皆に賞賛され褒められる自分自身であるとの本音を露呈した瞬間だったと思います。
このように感じたのは、率直に純粋にこれまで目にし、耳にしてきた安倍首相の言動の数々と、政府与党の動向一つ一つを順序だてて丁寧に追っていくと、おのずとその背後、水面下に隠された本音の野望や国民軽視のいい加減さが如実に感じとらざるを得ないからです。とりあえず今夏参議院での安保法制の強行採決の流れに至る巧妙なシナリオ運びの件は、ひとまずここでは控えるとしても、今回のシリア危機に対しては、これまで動かず関与せずの無関心ぶりから、世界から非難されていた日本政府が、ここにきて降ってわいたような、しかも国連総会の舞台をわざわざ利用しての安倍首相の演説は、まさに露骨なプロパガンダであり、見え見えのアピール戦略ととらざるを得ません。シリア危機のこれまでの経緯と実情、今後の難民問題の打開策・解決策等について以下に意見を述べさせていただきたいと思います。
●シリア危機と難民問題の現状
シリア危機にともない現在、ヨーロッパには第2次世界大戦以降最大規模と言われる移民が押しよせています。そもそもこの難民問題に世界が注目するようになったのは、皆さんの多くがご覧になったことと思いますが、先月9月2日トルコの海岸の波打ち際でうつぶせになって横たわっていた3歳のシリア難民の男の子の亡骸の映像と写真が世界に配信されたことがきっかけでした。この事故ではギリシャの島に向かう途中ボートが高波で転覆し一緒に乗っていた母親も5歳の兄も命を落としたそうですが、そもそも地中海を渡る途中で命を落とした人は、今年だけで3000人近くにものぼるそうです。そして難民問題の深刻さを訴えたこの映像と写真がきっかけとなり、これまで慎重だった世界のより多くの指導者を動かし始めたと言われています。UNHCR〈国連難民高等弁務官事務所〉によると、今年中東やアフリカなどから地中海を渡ってヨーロッパに入った人は、40万人を超えましたが、この数字は去年1年間の数の2倍です。彼ら彼女らは最終的には手厚い社会サービスが受けられるドイツや北欧を目指しています。ちなみにドイツには今年すでに45万人以上が入国しましたが、報じられる難民たちをドイツ市民が飲み水や食べ物、衣類、花束を渡し、心温かく迎い入れる光景は、難民を受け入れてきたドイツならでの慈愛や優しさが感じられます。ちなみにドイツに入国した人たちは待機施設に滞在しながら難民認定の審査を待ちますが、その間食事だけでなく生活に必要な現金も支給されるそうです。ドイツ政府は今年一年間に難民申請する人は80万人、あるいは去年の5倍の100万人に達する可能性があるとみており、難民のための施設の建設、語学教育、職業訓練など日本円で1兆円以上拠出することを決めています。難民受け入れにあたっては、様々な理由から反対や賛成しかねる人々の意見も少なくありませんが、ドイツはあくまで受け入れを続ける方針です。これはひとえに難民の保護を憲法の基本法で定めているからです。ナチス時代弾圧や迫害によって多くの罪もない人々を死に追いやった反省から助けを求める人々を受け入れる、この精神が難民受け入れの根底にあるのです。一方、ドイツ以外のヨーロッパの国々も、世論に押される形で受け入れを表明しています。16万人もの難民を各国が分担して受け入れようとしたEU全体での難民受け入れ提案は合意に達しませんでしたが、フランスは2年間で2万4千人の受け入れを表明。イギリスは5年間で2万人に増やし、フィンランドは去年の10倍近い3万人を受け入れ、スウェーデンは今年7万人の難民申請を見込んでいます。また難民の受け入れは、ヨーロッパだけでなく大西洋をまたいだアメリカやオセアニア、南米の国々も相次いで表明していました。アメリカが1万人、オーストラリアも国際社会に貢献すべきとの世論に押され1万2千人の受け入れを表明。南米の国々もベネズエラの2万人をはじめ各国が相次いで受け入れを表明しています。ところが9月以降世界各国が人道上の理由から受け入れを続々と表明した後も、9月中旬を過ぎても、日本政府からは受け入れの言葉は何も聞かれませでした。しかもそもそも難民の認定は日本では狭き門で、日本で難民申請をしたシリア人63人のうち、これまで認定されたのはたった3人でした。ちなみに世界の主要国の中で、シリア周辺国に逃れている難民の移住先として受け入れに応じていないのは9月中旬時点で日本、ロシア、韓国、シンガポールだけで、その人道精神のかけらも感じられない姿勢には、世界中から非難の声が上がっていました。日本は財政面で貢献しながらも、難民の受け入れにはとても閉鎖的な国だと世界からはみられているのです。まさに「積極的平和主義」をあそこまで高らかに得意げに世界に向けて発信したはずの国が、実は口先だけで、言行不一致のいい加減さの実態が、すでに世界の様々な国々に感じ取られ始めていた矢先のタイミングで、今回の演説が行われた訳です。
ちなみに世界には紛争や迫害により住む家を追われ保護を求めている人はおよそ6千万人とも言われています。シリア難民も周辺の国々だけにゆだねるのはもはや不可能です。日本は、国境を越え世界の隅々まで積極的平和による貢献をするとはっきりと明言したのです。一方、得意げに安保法制を掲げ、世界中のあちこちに出向きアメリカの言いなりとなり、アメリカ側の主観的な正義に単純に同調・賛成して、結果自衛隊員の命を危険にさらし、顔も知らない他国の兵や市民を殺傷する活動に力を注いでいる場合ではないんです。救い求める難民の方々の打ちひしがれた姿、逆にドイツに迎えられた時の絶望の淵から救われ、一筋の光明の光が差したような人々の安堵の表情を見るにつけ、単純にお金だけ出して国際社会における責任を放棄するようないい加減な態度はあらため、今こそ日本にしかできない貢献策を講じてほしいと思います。
●日本にしかできない難民支援策と役割
日本には、確かに言葉の壁や文化、風習の違い、そもそもの受け入れ可能な自治体の少なさなど、単純に考えればすぐに大多数の難民を受け入れるには、整えなければならない環境・仕組みの問題が山積しています。しかし、日本ならではまだまだやれることはいくらでもあります。「人道的配慮からひとまず日本に入国してもらい、申請が下りるまでの長期滞在を可能とする仕組みと環境を整える」東日本大震災をはじめ大災害を数多く経験した日本ならでは、そのためのノウハウと経験があるはずです。また、家族の絆を人一倍大事にする日本ならでは、「取り残された離れ離れのご家族が現地にいれば、優先して呼び寄せられるように、特別にビザをスピーディに発給する」「高度な医療サービスを提供すべく、ひとまず重い病気や怪我をした方を優先的に入国させ、治癒回復するまでの間、治療に徹する」「若者・学生を率先してあずかり、一定の滞在期間中に日本ならでは得られる知識や技術を習得してもらい、いずれまた再び祖国に帰国し復興に貢献してもらう人材を育てる」くわえて、単純にお金を出すだけの支援でない「日本ならではのメンタルケア面も含めた被災者支援のマインドを持った支援員を現地に派遣し、日本以外の選択肢も含めた難民サポートをする施策」も考えられます。
●難民支援における国際社会の調和と団結のための真の積極的平和活動
シリア危機に端を発する難民の悲劇は決して対岸の火事でなく、地球規模での同じ人間、同胞の危機です。しかも、集団的自衛権行使が現実味を帯びる将来を展望すると、決して好ましくなく絶対起こってほしくないことですが、万一の場合、日本が複雑化した国際情勢の中で他国の戦争に巻き込まれ、テロの本格的なターゲットとされ、最終的には大規模な戦場と化し、多数の被災者とともに難民が発生する事態も、全くあり得ない話ではないと思います。人が生きるか死ぬかの瀬戸際の苦しみにのたうちまわり本当に困っているときには、もはや国籍も人種も民族も宗教も貧富も関係なく、救いの手を差しのべたいものです。今こそ難民の悲劇を防ぐために世界各国が責任と負担を分かち合うよう求められているのです。
さて再び話を国連に戻しますが、現実を見ると、これまでシリア危機に際して、常任理事国アメリカとロシアの対立が影を落とす中、国連の安全保障理事会は実質機能不全を起こし、シリアの内戦を終わらせる取り組みは中断したままなのが現状です。まずは内戦を終わらせるための様々な有効施策を、国連をはじめ関係国が包括的に一致協力して打ち出し、着実に実施していくことが求められます。そのために、日本がなすべきことはまさに真の「積極的平和」の理念に基づいた率先垂範による実践です。これまで上述してきた通り、日本には単なるうわべだけの形式的な財政支援でない、血の通った心のこもった、顔の見える支援をしてゆくことが最も必要とされているのではないでしょうか。と同時に、国連安保理の常任理事国になるためにエネルギーを傾ける前に、むしろアメリカとロシアの対立を中和・仲介させるなどして、国連全体が同じベクトルで一致協力し、本来の世界規模での総合力を発揮できるように働きかけていくことにこそ、日本ならではの役割、存在意義やアイデンタティが発揮できることと思います。そしてそのためには、世論の力は重要です。私たち国民もすべて政府にばかり責任や役割を押し付けるのでなく、一人一人が難民問題、その背後、根底に横たわる差別・偏見・迫害・虐待・貧困等の問題や心の問題にも真正面から対峙し、考え、自らやれる範囲からでも、意識改革と行動変容につとめ、日本をより心豊かな国に変えていくことが望まれると思います。今私たち一人一人にも、真の積極的平和の役割が問われているのです。